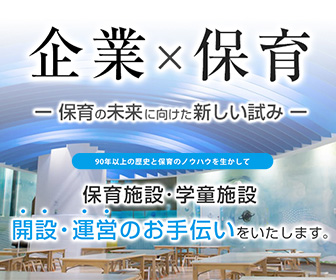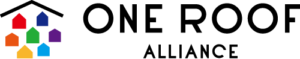「3歳になったけど周りの子と比べて成長がゆっくりに感じる」
「3歳児に対して、どのように関わり方を変えていけば良いか知りたい」
など、3歳児の成長や関わり方についてお悩みの方も多いのではないでしょうか?
3歳の子は、まだまだ甘えたい気持ちはあるけれど、気持ちはお兄さんお姉さんになっていたりします。自分でできることは自分でやろうとしますが、できないと大人を求める姿が多いです。できたことを褒めて自信に繋げていくことで、少しずつ自立していきます。
3歳児は、0歳児~2歳児と比べてできることが増えていく反面、どのようなことは避けた方が良いのか、親がどこまでサポートすべきなのか、判断が難しいポイントも多いですよね。
そこで今回は、3歳児の発達の特徴や目安について解説しながら、意識しておきたい関わり方と3歳児におすすめの遊びについて紹介します。
また、保育現場を知る当法人の知見をもとに、現役職員の所感や楽しみ方のアドバイスも掲載していますので、ぜひ参考にしてください。
目次
3歳児の発達の特徴
厚生労働省が取りまとめた「保育所保育指針」では、3歳児には以下のような成長や発達の特徴が見られると記されています。
| この時期においては、運動機能の発達により、基本的な動作が一通りできるようになるとともに、基本的な生活習慣もほぼ自立できるようになる。理解する語彙数が急激に増加し、知的興味や関心も高まってくる。仲間と遊び、仲間の中の一人という自覚が生じ、集団的な遊びや協同的な活動も見られるようになる。 |
基本的な生活習慣が身に付く3歳ですが、具体的にどのような成長が見られるのでしょうか。
保育の現場のリアルとしては、3歳児は各家庭での過ごし方や子育て感で、個々に違いが現れやすい年齢であると感じています。0・1・2歳から比べると、3歳は幼児への入り口でもある反面、家庭でまだまだ乳児のように接され続けていると食事を自分で食べすすめることが難しく、口に運んであげないと食べないといった様子も多々あります。まだまだ甘えていたい年齢でもあるので、子どもの気持ちを受け入れながらも、自分でできることはやっていけるように対応することが大切です。言葉の面では、具体的にたくさんの言葉を使うことで語彙が増えていく年齢でもあります。大人が先回りで察するのではなく、言葉でのコミュニケーションも意識してとるようにしていくと、大人にも自分の気持ちを発信できる子どもになると考えています。
上記をふまえつつ、まずは一般的に定義付けされている3歳児の成長について、身長や体重、言葉・運動能力、精神面・生活面などにおける特徴を解説します。
身長・体重の特徴
3歳児の身長・体重は、月齢によっても差があります。3歳児の月齢ごとの平均身長・平均体重を男女別に見ていきましょう。
| 3歳児の平均身長と平均体重 | ||||
| 男の子の身長 | 男の子の体重 | 女の子の身長 | 女の子の体重 | |
| 3歳0カ月 | 93.3cm | 13.7kg | 92.2cm | 13.1kg |
| 3歳1カ月 | 94cm | 13.9kg | 95.8cm | 13.3kg |
| 3歳2カ月 | 94.6cm | 14.0kg | 93.5cm | 13.4kg |
| 3歳3カ月 | 95.1cm | 14.2kg | 94.1cm | 13.6kg |
| 3歳4カ月 | 95.7cm | 14.4kg | 94.7cm | 13.8kg |
| 3歳5カ月 | 96.3cm | 14.5kg | 95.3cm | 13.9kg |
| 3歳6カ月 | 96.9cm | 14.7kg | 95.9cm | 14.1kg |
| 3歳7カ月 | 97.5cm | 14.8kg | 96.5cm | 14.3kg |
| 3歳8カ月 | 98cm | 15.0kg | 97.1cm | 14.4kg |
| 3歳9カ月 | 98.6cm | 15.1kg | 97.7cm | 14.6kg |
| 3歳10カ月 | 99.1cm | 15.3kg | 98.3cm | 14.8kg |
| 3歳11カ月 | 99.7cm | 15.4kg | 98.9cm | 15.0kg |
参照:低身長の基準|日本赤十字社芳賀赤十字病院
子供の平均体重・男子(男の子)版|スクスクのっぽくん
子供の平均体重・女子(女の子)版|スクスクのっぽくん
上記はあくまで平均値であり、平均に満たないからといって過度に心配する必要はありません。一方で、低身長や低体重の背景には、なんらかの要因が隠れている場合もあります。
3歳児の身長に関する詳しい情報や、受診すべきかを判断する目安については、以下の記事で詳しく解説していますので、こちらもぜひ参考にしてください。
関連記事:3歳児の身長・体重の目安は?伸びない要因と伸ばすために意識したいこと
言葉の発達の特徴
3歳児の言葉の発達では、以下のような特徴が見られます。
- 自分の名前や年齢を聞かれて答えられる
- 3語文が話せるようになる
- 「お腹が空いた」「眠い」「かゆい」など状態を言葉で伝えられる
- 大人の言葉・口癖を模倣するようになる
語彙力が急速に増える3歳児は、大人の話す言葉や口癖を模倣し始める時期でもあります。大人の声掛けや言葉遣いに配慮しながら、接することが大切です。
また、この時期にしかない言い間違えや可愛い表現が見られるため、記録しておくのも良いでしょう。筆者の子は、3歳頃「おくすり」が言えずずっと「おすくり」と言っていました。このような姿が見れるのも、3歳ならではの成長過程として楽しみたいですね。
運動能力の発達の特徴
3歳児の運動能力は、以下のような発達の特徴が見られます。
- 片足で「ケンケン」ができるようになる
- 階段の昇り降りを足を交互に出してできるようになる
- ボール投げ・キャッチができるようになる
- 小さな段差をジャンプできるようになる
- 鉄棒にぶら下がれるようになる
個人差があるため、このような動きができる子もいれば、できない子もいます。遊びの中に運動を取り入れながら、少しずつ運動能力を伸ばせるように取り組んでいくと良いでしょう。
社会性・遊びの特徴
3歳児は、社会性においても成長が見られる時期です。これまでは一人遊びや保護者(大人)との遊びが中心でしたが、3歳児頃からは同年代のお友達と遊ぶ様子も見られます。お友達におもちゃを譲ったり、順番を待ったりして、相手を思いやる気持ちが芽生え始めるのも特徴です。一方で、「こうしたい!」という自我もあるため、少しずつ自己主張と思いやる気持ちのバランスを学び始めます。
食事内容の特徴
3歳児は、1~2歳頃と比べて食事の面でも成長が見られます。落ち着いて席に座って食事ができるようになったり、好き嫌いがはっきりし始めたりする傾向です。また、3歳の後半頃になってくると、お箸を使って食事ができるようになる子もいます。食事量も増えてくるため、3食で必要な栄養が摂れない場合は、間食を含めた栄養バランスを意識することが大切です。
3歳児の発達特徴に当てはまらない場合はどうすれば良い?

子どもの成長は、個々の家庭の状況や経験などでも変わってくると思います。月齢による差も大きく、兄や姉がいるのといないのとでの違いもあるので、園の中で年上児と関わりをもつうちに、できることが増えてくることもあります。とはいえ、もし気になる様子がある場合には、早めに発達相談をする方が、子ども自身の「困り感」が解消されるので検討してみるのも良いでしょう。
上記のように3歳児の発達特徴は子どもによって異なります。たとえば、「〇〇はできるけど△△はできない」など、できることとできないことにムラがあるケースです。これは時間が経つにつれて解消される場合もあります。
しかし、3歳児の発達特徴に当てはまらないと、不安になることもありますよね。発達特徴に当てはまらない場合、発達障害を気にする方も多いでしょう。発達障害とは、生まれつき脳機能の発達になんらかの障害を抱える状況のことです。コミュニケーションや社会性、行動面に特徴が見られることがあります。適切なタイミングに受診して診断を受け、対応方法を学ぶことで本人の特性に合わせた対応方法や成長の促し方を学べるでしょう。
ここでは、発達の個人差に関する情報や、発達障害の心配がある場合の受診目安について解説します。
発達には個人差がある
3歳児の特徴に当てはまらないからといって、過度に心配する必要はありません。発達には個人差があるうえに、3歳0カ月と3歳11カ月では1歳近い開きがあるため、できることにも違いがあります。「同年代の子と比べてできないことが多いのでは」と気になる場合は、その子の成長に合わせて少しずつ、遊びの中に成長につながる要素を取り入れてみると良いでしょう。
発達障害の心配がある場合に受診する目安
2歳頃までと比べて、幼稚園や保育園などの集団生活に加わるケースが多い3歳児は、発達障害の兆候が見られる時期でもあります。ほかの子と比べて特徴に違いが見られる場合は、一度専門機関に受診して診断を受けるのも良いでしょう。
滋賀医科大学によると、発達障害の兆候として、3歳~4歳頃に以下のような特徴が見られると指摘されています。
| 早いうちから子どもの特性を理解し、適切な対応ができれば、子どもの心を安定させ、その子どもが持っている個々の能力を伸ばしていくこともできます。また、早い段階から適切な対応を行うことで、自尊感情の低下や劣等感・孤立感の強まりなどの心理面の問題や、不登校や周囲の大人への反抗的な言動などの行動面の問題を予防することができます。
◆発達障害の兆候 3歳~4歳:「気になる」部分が目立ち始める時期 偏食が激しい。名前を呼んでも振り返らない。落ち着きがない。何度言っても言うことを聞かない。特定のおもちゃに執着する。一人で遊ぶ方が好き。一人にされても泣かない。 |
3歳児の特徴に当てはまらないだけでなく、このような兆候が見られた場合は、一人で悩まず早めに専門機関を受診して、接し方のアドバイスを受けることをおすすめします。
3歳児の発達の特徴に合わせた関わり方
3歳児はできることが増えるとはいえ、まだまだできないことも多くあります。そのため、以下のポイントを意識して、関わっていくことが大切です。
- 自己主張をまず受け止める
- できないからとすぐに大人が手を出さない
- やってはいけないことをきちんと伝える
それぞれ3歳児の特徴を踏まえて、意識しておきたい大人の関わり方について詳しく解説します。
自己主張をまず受け止める
3歳児はできることが増えてくる反面、まだまだ甘えたい時期でもあります。そのため、まずは自己主張を受け止めてあげたうえで、どうしていけば良いか、大人が導いてあげることが大切です。気持ちを受け入れてもらえた経験が大人に対する信頼感につながり、困ったときに自分から助けを求められるようになります。もしやってはいけないことをしてしまった場合でも、まずはなぜその行動をしたのか聞いてみて、したかったことを受け入れたうえで、適切に指導しましょう。
できないからとすぐに大人が手を出さない
3歳児と接するうえで重要なのは、できないからといって大人がすぐに手を出さないことです。着替えや食事など、日常生活においてできることが増える3歳児ですが、まだまだできないことも多くあります。
乳児時期は大人がすべて身の回りの世話をしてきましたが、3歳児にも同じように接すると、できることが増えるきっかけを損ないかねません。できないときは、「こんな風にすると良いよ」「ここをこうしてみよう」など、アドバイスやお手本を見せたりして、チャレンジさせてあげましょう。できたときは、たくさん褒めてあげてくださいね。
やってはいけないことをきちんと伝える
3歳児は、ルールを覚えるうえで大切な時期です。社会のルール、友だちとの接し方、危険を回避するためにやってはいけないことなど、教えなければならないことはきちんと伝えるようにしましょう。
なぜやってはいけないのか、代わりにしても良いのはどのようなことなのかを落ち着いて話すことが大切です。また、泣いて話を聞く体制ができていないときは、落ち着くのを待ってあげたり、気持ちに共感してあげたうえで、どうすれば良かったのかを伝えると良いでしょう。
保育現場では、保護者の方が子どもの言いなりになっている様子も多くみられます。3歳児は自己主張もはっきりとしてくるので、言い聞かせることは簡単ではありません。大切なのは、子どもの主張をまず大人が受け止め、今はそれになぜ対応できないのかをしっかりと伝えることです。0・1・2歳のときとは違い、3歳児は大人が誤魔化してはいけない年齢でもあります。そのため、保育現場では一貫性をもって関わるように心がけています。気持ちの切り替えに関しては、言葉の理解もあるので先に待っている楽しみなどを伝えることで、今は泣くのをやめようなど子どもなりに切り替えをすることができるようになってきます。
3歳児は、大人の接し方次第でできることが大幅に広がっていく時期です。次項では、成長につながるポイントを盛り込んだ3歳児と楽しめる遊びのアイデアを紹介します。
3歳児の特徴に合わせた遊びのアイデア

では、3歳児の特徴に合わせた遊びを取り入れるにはどのようなアイデアがあるのでしょうか。ここからは以下について具体的にどのような遊び方があるのか、3歳児にとってどのようなメリットがあるのかを詳しく解説します。
- 集団遊び
- ゲーム遊び
- 運動遊び
- ごっこ遊び
集団遊び
3歳児の社会性を伸ばすために、おすすめの遊びが集団遊びです。集団遊びは、友だちとのやり取りや協力を通じて「一緒に遊ぶこと」を学べます。具体的には、以下のような取り組みが集団遊びです。
- じゃんけん列車
- 新聞紙島
- だるまさんがころんだ
- フルーツバスケット
3歳児はまだ複雑なルールを覚えられない子も多いので、まずは簡単なルールでチャレンジしてみましょう。大人がお手本を見せたり、手伝ったりして楽しく遊べるようにサポートしてあげてくださいね。
ゲーム遊び
ゲーム遊びは、ゲーム性がある遊びです。挑戦とクリアする達成感が味わえる点が特徴で、3歳児の「やってみたい」という気持ちを育めます。具体的には、以下のような取り組みがゲーム遊びです。
- 積み木でドミノ
- ボールで的当て
- 宝探しゲーム
- 言葉集めゲーム
言葉集めゲームは、「ま」のつくもの「た」のつくものなど、お題に合うものを部屋の中から探してくるゲームです。頭文字ではなくても、含まれていたら成功にして、取り組みやすいルールにしてあげましょう。
ゲーム遊びでは、クリアしやすい状況をつくって取り組ませてあげることがポイントです。「できた!」という気持ちを経験していくうちに、より難しいことにもチャレンジする意欲につながります。
運動遊び
運動遊びは、3歳児の運動能力を伸ばすうえで重要な遊びです。たとえば、以下のような遊びが挙げられます。
- 色探しゲーム
- 虫取り網で紙吹雪キャッチ
- かみなりゲーム
- うちわ風船リレー
色探しゲームは、指定した色のものを探すゲームです。色とりどりのカラーシールを部屋の中に貼って、遊ぶ方法もあります。また、かみなりゲームは鬼役の「かみなり!」の言葉に合わせて、おへそを隠して遊ぶゲームです。「かみひこうき」「かばん」など、ほかの言葉を織り交ぜて遊ぶのも良いですね。
これらの遊びは、室内でも楽しめます。屋外で遊ぶ場合は、フラフープで「けんけんぱ」や、縄跳びを使った「へびにょろにょろ」など、ジャンプにチャレンジしてみるのもおすすめです。
ごっこ遊び
ごっこ遊びは、表現力を培うのに役立つ遊びです。3歳は、大人の模倣をする行動・言動がよく見られる時期のため、ごっこ遊びも楽しめます。
- 忍者ごっこ
- ものまねごっこ
- 収穫ごっこ
- おままごと
収穫ごっこは、野菜や果物を工作して、収穫のまねをする遊びです。大根をつくって牛乳パックから引き抜いたり、ロープで木の枝を模してつるしたりんごを採ったりして遊びます。工作のバリエーションも豊富なので、手指の動かし方を学ぶきっかけとしてもおすすめです。
本項で紹介した3歳児向けの遊びについては、以下の記事で詳しい取り組み方やサポート方法のポイントについて解説していますので、こちらもぜひ参考にしてください。
関連記事:3歳児と楽しむ室内遊びのアイデア16選!集団遊び・運動遊び・ゲーム遊び・ごっこ遊びをそれぞれ紹介
3歳児の特徴に合わせた関わり方で成長をサポートしよう
3歳児は一人でできること、やりたいことが増える一方で、思うようにいかず怒ったり・泣いたりすることもよく見られます。
3歳児に関わるときは、まず「やりたい!」という気持ちを大切にしてあげることがポイントです。
できなかったからとすぐに大人が代わってしまうのではなく、どうすればうまくいくかアドバイスしたり、つまづいている部分だけサポートして、「できた!」という達成感につなげましょう。
小さな成功体験の積み重ねが、新たな「やりたい!」につながります。お子さまの成長に合わせたサポートをしながら、これからの成長を見守っていきたいですね。