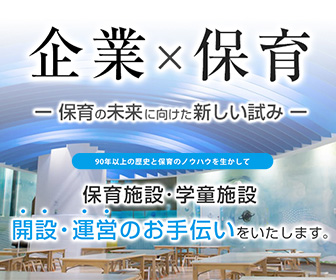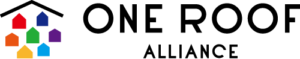「4歳児の発達の特徴はどのようなものだろう?」
「4歳児の反抗が増えて、どう接したらいいかわからない」
このようにお悩みではありませんか?
4歳児は生活面で自分のできることが増えてきます。でもまだまだ甘えたい気持ちがあるので、自分でできないことがあると大人に伝えてくることも多々あります。また、体力もついてきて動きも活発になりますが、体の動かし方がまだ難しい子どももいるので、ケガを未然に防げるように、運動面を伸ばしていけるような活動を考えていくことも大切です。
まさに4歳児は自立心が芽生える時期ですが、同時に反抗やわがままが増えることもあります。これは正常な成長の一環であり、適切な接し方を知ることで、4歳児の発達をスムーズにサポートできるでしょう。
そこで本記事では、4歳児の特徴や発達の目安、しつけや接し方のポイントを解説します。保育の現場で感じるリアルな意見も盛り込んでいますので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
4歳児の成長・発達の特徴とは?

個々に合わせた対応はどの年齢も必要なことですが、特に4歳児は集団の中での理解力や個々の苦手なことに目を向けて大人が介助し、関わるようにしています。3、5歳の年齢に比べると個人差が見られると思います。苦手なことを家庭に伝えて、家でも気に掛けてもらえるような配慮をすることもありますね。
身体の発達が進み、骨格や筋肉がしっかりしてくる子も多い4歳児。上記を踏まえつつ、一般的な成長・発達の特徴を見ていきましょう。ここでは、以下を詳しく解説していきます。
- 4歳児の平均身長・体重(発育の目安)
- 4歳児の運動能力の発達
- 4歳児の知能や言語能力の成長
- 4歳児の社会性の発達
※成長のスピードには個人差がありますので、ここで紹介する成長・発達の内容は、あくまで目安として参考にしてみてください。
4歳児の平均身長・体重(発育の目安)
厚生労働省が2010年に実施した乳幼児身体発育調査によると、4歳児の一般的な成長の目安は以下のとおりです。
| 男児 | 女児 | |
| 身長 | 約105cm | 約100cm |
| 体重 | 約16kg | 約15kg |
同じ4歳児でも、高身長の子もいれば小柄な子もいます。身長や体重が目安と違っていても、食欲があるか・元気でよく遊んでいるかなど、子どもが健康的に成長しているかどうかをチェックしてみましょう。
4歳児の運動能力の発達
4歳児は運動能力が大きく発達し、体のバランス感覚や筋力が向上しやすい時期です。個人差はありますが、3歳児の頃よりもさまざまな動きがスムーズにできるようになってきます。例えば、
- スキップができる
- 片足でケンケンが左右どちらの足でもできる
- 約20mを全力で走れる
- ボールを狙った方向に投げられる
- 散歩が1時間以上できる
上記のように、4歳児になると全身運動とともに細かな動きもできる子が増えてきます。
4歳児の知能や言語能力の成長
4歳児になると、以下のように知能や言語が発達し、周囲の言葉をどんどん吸収して、自分の経験や感情を言葉で伝えられるようになってきます。
- 語彙数が1500~2000語に増える(日常会話を理解し、受け答えがスムーズになる)
- 「なんで?」「どうして?」と質問が増える(知的好奇心が旺盛になる)
- 「だって◯◯だから」と自分の意思を言える(理由のある自己主張ができる)
- 1から10まで数えられる子もいる(数字に興味を持ち始める)
子どもの話をしっかり聞き、「それでどうなったの?」「何が楽しかった?」などと質問すると、会話が広がり、コミュニケーションをどんどん楽しめるようになるでしょう。
4歳児の社会性の発達
4歳児は友達への興味が高まり、主に以下のような協調性や社会的スキルが発達する時期です。
- 鬼ごっこやかくれんぼなど、ルールのある遊びを理解し、友達と一緒に楽しむ
- 遊びの中で順番を守れる
- 「◯◯で遊ぼう」「かして」など、他の子どもに意思を伝えられる
上記のように、友達と関わりながら遊ぶ4歳児の姿に成長を実感するママやパパも多いのではないでしょうか。
次の章では、4歳児頃の子どもが迎える「4歳の壁」について解説します。
「4歳の壁」とは?4歳児の性格と行動の変化

「さっきまで機嫌がよかったのに、急に大泣き…」といったように、2歳児のイヤイヤ期に続き、4歳児の突然の反抗や感情の変化に戸惑う保護者の方も多いのではないでしょうか。この時期は「4歳の壁」と呼ばれ、4歳児の成長の証でもあります。
「4歳の壁」とは、4歳児が自我の芽生えとともに、自己主張と感情のコントロールの間で葛藤しやすくなる時期を指します。反抗や不安定な行動が増えるのも、その発達過程の一部です。
4歳児になると、子どもの認知能力が大きく成長し、「自分と他人は違う」という認識が芽生えます。3歳児頃までは「親の言うことが正しい」と思っていた子どもも、4歳児になると「自分の考えは違う!」と主張する傾向があります。
ただし、自分の感情をコントロールする力は未熟です。そのため、「やりたいのにできない」「言いたいことがうまく伝わらない」といったストレスを感じやすくなり、以下のような言動が目立つようになります。
- かんしゃくを起こす
気に入らないことがあると、泣く・怒る・大声を出す - 自分の意見を通そうとする
「今すぐやりたい!」「自分で決めたい!」という意識が強くなり、親の指示を嫌がる - 言葉が強くなる
「もう嫌い!」といった親を傷つけるような言葉を使うことがあるが、悪気があるわけではなく、感情表現の手段が未熟な状態にある - 甘えと反抗を繰り返す
「一緒にいて!」と甘えるかと思えば、急に「もういや!」と突き放すこともあり、心の成長が進む中で、気持ちが揺れ動きやすい時期にある
自分と相手の気持ちのすれ違いが起きたときに、それぞれの気持ちをわかりやすく言葉にして伝えて仲介することが重要です。
それでは、4歳の壁で困ったとき、具体的にどのような対応をすれば良いのでしょうか。次項で見ていきましょう。
4歳児のしつけ・接し方のポイント
子育てをする中で、4歳児のしつけや接し方についてお悩みの方も多いでしょう。保育の現場では、以下の点を意識して4歳児と接しています。
4歳児は物事の良い悪いの判断がつく時なので、人に迷惑をかけることをしていないかなどは、自分自身で気付けるようにしていかないといけません。自分の気持ちを優先するだけではなく、「自分だけが良いのではなくて、相手はどうなのか?」を考えさせるきっかけを作り、一緒に考えていくことが大切です。
その他、4歳児のしつけ・接し方について、以下のポイントも押さえておくと良いでしょう。
自立心を尊重する
4歳児になると、さまざまなことを「自分でやりたい!」という気持ちが強くなってきます。そのため、服を着る・食事の準備をする・靴を履くなど、4歳児が自分でできそうなことはやらせてみるのがおすすめです。
多少時間がかかっても、成功体験を積むことで「自分でできた!」という自信につながりやすくなり、4歳児が納得して次の行動に移れるでしょう。
感情に寄り添う
思い通りにいかず、かんしゃくを起こしたり、突然泣いたりすることもある4歳児には、「ダメ!」より「こうしようね」を意識して伝えると良いでしょう。
まずは「◯◯したかったんだね」と4歳児の気持ちを受け止め、その上で「どうすればよかったかな?」と一緒に考えるのがおすすめです。このように感情に寄り添って接すると、してはいけないことといったルールを4歳児が理解しやすくなります。
最後に、保育の現場から見た、4歳児の発達が気になる際に確認したい点について解説します。
4歳児の発達が気になるときのチェックリスト
4歳児の子どもを持つ保護者の方の中には、発達が気になるという方もいらっしゃると思います。
保育現場では、4歳児と接する際、発達に気になることがないか、以下のようなことを意識してチェックしているのでぜひ参考にしてみてください。
園生活を乳児から経験している子どもたちは積み重ねがあり、発達に合わせて園で援助をしながら生活しています。2歳でここまでできるようになっていよう、3歳はここまでできるように持っていこうなど、その子どもに合わせて発達を追っています。
しかし、やはり乳児期の時に苦手なことは幼児クラスに進級しても苦手なままのことが多々あります。道具(ハサミやのり)を使って作業をすることができるか、集団から外れていないか、言葉の理解力などは園生活の中でチェックをしています。
また、トラブル時に言葉で伝える前に手が出てしまうなど、抑えきれない感情がある様子などもチェックをしています。
4歳児の発達は個人差が大きく、どのような基準で考えれば良いのか迷うこともあるはずです。そこで、4歳児の発達を確認するためのチェックリストをご紹介します。
体・運動
- スキップ・両足ジャンプで前に跳ぶ・リズムに合わせて動けるなど、年齢に応じた運動ができる
- 座る・立つときにまっすぐの姿勢を保てる
- こぼさずに食事ができる
- 四角形を真似しながら描ける
- テニスボール位の大きさのボールを相手が受け取れるように投げたり、1m離れた場所から受け止められる
- サ行・ラ行などの発音が歪まないように正しい発音で話せる
言葉・知能
- 日常の挨拶や自分の名前・年齢などを言える
- 歌を多少間違えながらでも歌える
- 過去や未来のことを話す(時間の概念がわかり始めている)
- 10分以上集中して遊べる
情緒・行動
- ぐずっていても、なだめるとすぐに泣き止みやすい
- 相手の気持ちがわかる
- 相手や自分を傷つけるような乱暴な行動はしない
社会性
- 同年齢の子どもと一緒に楽しんで遊ぶ
- 友達とルールを守って順番に物を使える
- 主な養育者に愛着行動を示す
- 年下の子どもや生き物に優しくしたり、かわいがったりする
上記のチェックリストに「できない項目がある=問題がある」とは限りません。あくまで成長を見守るためのひとつの指標として参考にしてください。
もし気になる点がある場合は、一人で抱え込まずに、保育園や幼稚園、小児科や発達相談・療育などの窓口に相談するのもひとつの方法です。
参照:DCD 支援マニュアル丨厚生労働省 (CLASP)の運動に関する項目、幼児児用(3~6 歳)
4歳児は成長を楽しみながら見守りましょう
4歳児は、言葉や運動能力が大きく発達し、自立心や社会性が育つ時期です。とはいえ、成長には個人差があり、子どもによって発達の進み具合も違います。
この記事で紹介したような保育現場の実際の意見も参考にしながら、4歳児の成長を温かく見守ってみてはいかがでしょうか。