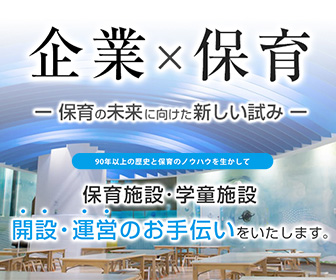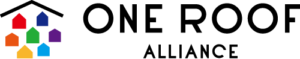年少(3歳児)クラスになると、指先が比較的自由に動くようになり、はさみやのりなどの道具も上手に使えるようになります。製作遊びをたくさん導入したいと思っている保育士の方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、年少クラスにおすすめの製作アイデアを10個ご紹介します。発達の特徴や保育のねらいなども併せて解説するので、ぜひ参考にしてみてください。保育アイデアを増やし、楽しく製作遊びを行いながら子どもの発達を促しましょう。
年少児(3歳)の発達の特徴は?

年少児(3歳頃)は、どのような発達が見られるのでしょうか。ここでは、まず3歳児の身体的な発達、精神的な発達の特徴を詳しく紹介します。
身体的な発達
3歳頃は脳神経が発達し、運動能力が高まる時期です。2歳児に比べると自分でできることも増え、活発に体を動かすようになります。3歳ごろに見られる身体的な発達の特徴は以下の通りです。
- つま先立ちができる
- 片足ずつ階段を上れる
- 自転車のペダルを難なくこげる
- 線に沿ってはさみで切れる
- 積み上げる、つまむなど細かい動作ができる
- 歩く、走る、ジャンプなどの動作をスムーズに行える
- 排泄や歯磨きなど身の回りのことが自分でできる など
精神的な発達
体の発達だけでなく、思考力や情緒面の発達も著しい時期です。3歳ごろには、以下のような姿が見られます。
- 想像力が身に付く
- 表現する力が伸びる
- 好奇心や興味関心が強くなる
- 集中して物事に取り組む時間が長くなる
- 「自分でやりたい」という気持ちが芽生える など
3歳児は色々なことに積極的に挑戦するようになり、心も体もグンと成長します。精神的な発達も促せる内容の遊びを取り入れましょう。
年少クラスで製作遊びを導入するねらい
年少クラスで製作遊びを展開する際は、事前にねらいを定める必要があります。ねらいの一例は以下の通りです。
- 自分の力で作品を作り、達成感を味わう
- 道具の使い方を知り適切に扱うようになる
- 興味関心や好奇心を促し、主体的に活動に参加する
- 自身のイメージや気持ちを表現することの楽しさを味わう など
年少児の発達の特性の中から、伸ばしたい部分を見つけ、課題に即した遊びを展開することが大切です。そうすることで、子どもたちが学びを深めやすくなります。
年少クラスにおすすめ!製作遊び10選

年少クラスにおすすめの製作遊びを10個ご紹介します。年少児が自発的に取り組みたくなるようなアイデアをピックアップしました。季節ごとの製作アイデアと、作って遊べる製作アイデアを両方紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
【春】あおむし
春になると出てくる「あおむし」の製作アイデアです。スタンプを利用するので、年少児でも簡単に作成できます。
【用意するもの】
- 画用紙
- はさみ
- コンパス
- 野菜スタンプ(レンコンやオクラなど)
- 絵の具
- お皿
- 水
- のり
- マーカー
【作り方】
- 野菜を切ってスタンプを作る
- 画用紙にコンパスで円を描く
- お皿に絵の具と水を入れて混ぜる
※ここまでは保育者が行う - 画用紙の線に沿ってはさみで切る
- 切った画用紙に野菜スタンプを押していく
- あおむしの顔をマーカーで描く
- 触覚と顔、胴体をのりでつけて完成
【夏】花火
はじき絵という技法を使用した花火です。クレヨンが水をはじく習性を利用して、画用紙に色をつけます。きれいに色を発色させるためにも、クレヨンはしっかりと塗り重ねましょう。
【用意するもの】
- 画用紙
- クレヨン
- 黒や紺の絵の具
- お皿
- 水
- 筆
【作り方】
- 画用紙にクレヨンで花火を描く
※クレヨンでしっかりと色をつける - お皿に絵の具と水を入れて混ぜる
- 筆で、クレヨンの上から色をつけたら完成
【秋】どんぐりケーキ
どんぐりを可愛くデコレーションして作るどんぐりケーキです。実際に自分で拾ってきたどんぐりを使用すると、製作時の楽しさが倍増します。また、紙粘土は色付きのものがおすすめです。色とりどりのケーキが簡単にできあがります。
【用意するもの】
- 紙粘土
- 粘土板
- どんぐり
- プリンカップや紙皿など
- スパンコールやビーズ、モールなど
【作り方】
- 粘土板の上で紙粘土をこねる
- プリンカップや紙皿などに紙粘土を入れる
- どんぐりやビーズ、スパンコールなどを飾る
- モールを5cm程度に切る(ろうそくに見立てる)
- 空いたスペースにモールを刺して完成
【冬】鬼のお面
豆まきの際に使用できる鬼のお面です。自分で作ったお面を付けて豆まきをすると、いつも以上に楽しんでイベントに参加できます。眼鏡の形の部分は切るのが難しいため、保育者が先に仕上げ、材料の一部として提供するのが望ましいでしょう。
【用意するもの】
- 画用紙
- シール
- 毛糸
- ボンド
- はさみ
- マーカー
【作り方】
- 画用紙を眼鏡、髪の毛、角の形に切る
- 角の形の画用紙にマーカーで縞模様を描く
- 眼鏡の部分にシールを貼りデコレーションする
- 髪の毛の形の画用紙にボンドを塗り、毛糸を乗せる
- 各部品をボンドやのりで貼り付けて完成
こま
作って楽しい、遊んで楽しい手作りこまです。指先を使わなければ回らないため、手先のトレーニングにもなります。指先を動かすと脳への刺激になり、知育に良いといわれています。
【必要なもの】
- 紙皿
- ストロー
- ホッチキス
- マーカーや色鉛筆
- セロハンテープ
【作り方】
- 紙皿にマーカーや色鉛筆で絵を描く
- 中心に向けて1ヵ所切り込みを入れる
- 切った部分を数センチほど重ねてホッチキスで留める
- セロハンテープを貼り、切り込みの部分を保護する
- ストローを半分ほどの長さに切り、先に切り込みを入れる
- 紙皿の中心部分に切り込み部分をあて、セロハンテープで留めて完成
おばけ
紙コップからおばけが飛び出す不思議な製作アイデアです。作り方は簡単なので保育園や幼稚園でも気軽に製作できます。コップに穴を開ける作業は難しいため、保育者が先に済ませておきましょう。
【用意するもの】
- 紙コップ
- 小さめのビニール袋
- ストロー
- 画用紙
- はさみ
- のり
- セロハンテープ
- きり
- マーカー
【作り方】
- 画用紙におばけの顔を描き、ビニール袋に貼る
- 帽子や手なども装飾する
- ビニール袋の口の部分を小さくまとめ、ストローを差し込む
- ストローとビニール袋の口の部分をセロハンテープで固定する
- 穴の開いた紙コップに、ビニール袋とストローを入れる
- ストローを内側から紙コップの穴に通して完成
けん玉
日本の伝承遊びのひとつ「けん玉」をイメージした手作りおもちゃです。コップにボールを入れられるようにと何度も練習したりやり遂げたりする中で、集中力や達成感も味わえます。
【用意するもの】
- 紙コップ
- 毛糸(20cm程度)
- 新聞紙
- ビニールテープ
- はさみ
- マーカー
- シール
【作り方】
- 紙コップに絵を描いたりシールを貼ったりしてデコレーションする
- 1つめの紙コップの裏に糸をテープで付ける
- 1つめと2つめの紙コップの底を合わせてビニールテープで留める
- 新聞紙を紙コップに入る程度の大きさに丸める
- 新聞紙の玉と毛糸の先をビニールテープで巻き付けて完成
双眼鏡
双眼鏡の製作アイデアです。探検・お散歩などの際に持っていけば、子どもたちのモチベーションがアップすること間違いありません。双眼鏡で覗いたものをスケッチしたり、季節見つけや動物見つけなどに使用したりして、遊びをどんどん展開しましょう。
【用意するもの】
- トイレットペーパー
- 折り紙
- シール、スパンコールなど
- ホッチキス
- 紐やリボン
- ボンド
【作り方】
- トイレットペーパー2本にボンドを塗り、折り紙を巻き付ける
- スパンコールやシールなどを貼り装飾する
- トイレットペーパー2本を横に並べ、ホッチキスで留める
- リボンや紐を子どもの首が通るくらいの長さに切る
- トイレットペーパーの端と紐の端をホチキスで留めて完成
ブーメラン
紙コップで作るブーメランです。紙コップには飲み口の硬い部分だけ、事前に切り込みを入れておくと、子どもでも切り進めやすくなります。また、実際に投げて遊ぶ際は、園庭や遊戯室など広いスペースを用意しましょう。
【用意するもの】
- 紙コップ
- マーカー
- はさみ
- ホッチキス
【作り方】
- 紙コップに4ヵ所切り込みを入れる(等分になるように)
- 同じ状態の紙コップをもうひとつ作る
- 1つめの紙コップの外側にマーカーで絵を描く
- 2つめの紙コップを下に重ねて、羽の部分をホッチキスで留めて完成
カスタネット
牛乳パックで作るカスタネットです。牛乳パックとペットボトルのキャップがあれば簡単に作成できます。カスタネットや鈴、タンバリンなどいくつか楽器を作り、合奏遊びをしても楽しめるでしょう。
【用意するもの】
- 牛乳パック
- ペットボトルのキャップ
- セロハンテープ
- 画用紙
- マーカー
- ボンド
【作り方】
- 牛乳パックを1面ずつに切り分ける
- 1面を半分に折る
- 白い面に絵を描く(画用紙に描き貼り付けてもOK)
- 内側にペットボトルのキャップを2つセロハンテープで付けて完成
年少クラスで製作遊びを取り入れる際のポイント
年少クラスで製作遊びを取り入れる際は、いくつか押さえておきたいポイントがあります。子どもたちが楽しく、かつ主体的に取り組めるよう配慮しましょう。
興味関心にあった題材を選ぶ
子どもたちの興味関心にあった題材を選びましょう。子どもの発達や興味関心の内容と題材が合わない場合、「製作してみたい!」という気持ちが沸きにくくなります。
「先生に言われたからやる」「終わらせなければ遊べない」といった気持ちで活動に参加しても、そこから得られるものは少ないでしょう。
子どもたちの日々の様子を観察し、自分から思わず活動に参加したくなるような製作アイデアを取り入れることが大切です。
自分で作る達成感を大切に
年少児(3歳ごろ)の子どもは、「自分でやりたい」「一人でできる」といった気持ちが強くなります。その気持ちを伸ばせるように配慮するのがおすすめです。例えば、以下のようなことができます。
- カッターやキリを使うといった保育者でなければできない行程は、先に終わらせておく
- 材料の形や色など種類を多くして、選択肢を増やす
「全て自分で作った」と認識することで、強い達成感を味わえます。また、物事をやり切る楽しさに気付くことで、積極的に取り組む力や諦めない心なども養えるでしょう。
そのためにも、「子どもの目の前で保育者が仕上げる」「材料が少なすぎて製作の意欲がわかない」といったような状態にならないようにする必要があります。
個人の発達差に合わせて対応する
年少児は、年中や年長などの他の幼児期の子どもに比べると、まだ個人の発達差が大きい時期です。製作が得意な子もいれば、手先を細かく動かすことが苦手な子もいます。子ども一人ひとりの発達に合わせて、適切にサポートしましょう。
ただし、保育者が手伝いすぎると、個性が失われてしまう恐れがあります。声掛けをして励ましたり、見本を見せて分かりやすく説明したりしながら活動を促しましょう。
まとめ
年少(3歳児)は、心身が大きく発達します。特に「自分でやりたい」という自立心や積極性が育つ時期であるため、「難易度は高くないけれども、製作工程が複数に及ぶもの」がおすすめです。
また、けん玉やこまなど、作って遊べるものも年少児の製作物にふさわしいでしょう。保育の製作アイデアをご紹介した今回の記事も、ぜひ参考にしてみてくださいね。