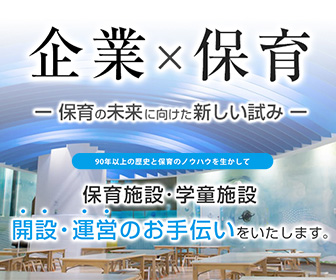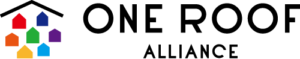「食育って本当に必要なの?」
「食育をしたいものの、何をしたらいいのかわからない」
「見本となる食育の例を知りたい」
という方も多いのではないでしょうか。
食育は子どもの健やかな成長を支える重要な取り組みです。食に対する知識や興味を育てることで、健康的な食生活の基盤を築くだけでなく、心の成長や社会性の発達にもつながります。
そこでこの記事では、食育の基本からメリット、家庭で実践できる具体的なアイデアをわかりやすくご紹介します。
また、この記事ではその道を究めたプロにお話を伺う「プロ育」の対談内容から、プロならではの食育についても触れております。プロ育を詳しく見たい方はぜひこちらも参考にしてみてください。
目次
食育とは?子どもに身につく5つの力
食育は、食育基本法で以下のように定義されています。
引用
“「生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきものと位置付けるとともに、様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てる」”
引用:食育基本法
また、厚生労働省は、乳幼児期の食育で育まれる力について、以下の5つを紹介しています。
①規則的にお腹がすく生活リズムを育む
②食事を味わって食べられるようになる
③誰かと食事をとりたいと思う気持ちが育まれる
④食事作りや準備に関わりたいと思う
⑤食や健康に主体的に関わろうと思う
参考サイト:『楽しく食べる子どもに~食からはじまる健やかガイド|厚生労働省
つまり食育とは、「乳幼児期から食に対する興味関心を育むことで、生涯にわたって健康で生きられる土台を作る教育である」とも言い換えられます。
そこで次の章では食育で育まれる5つの力について、もう少し深堀していきましょう。
食育を行うメリットとは?5つの力を深堀
子どもが食育を行うことで得られる力として以下を紹介しました。ここでは、この5つの力について詳しく解説します。
①規則的にお腹がすく生活リズムを育む
②食事を味わって食べられるようになる
③誰かと食事をとりたいと思う気持ちが育まれる
④食事作りや準備に関わりたいと思う
⑤食や健康に主体的に関わろうと思う
1. 規則的にお腹がすく生活リズムを育む
食育を行うことで、朝・昼・晩と毎日三食、決まった時間に食事がとれるようになると、規則正しい生活リズムが生まれます。その結果、思いっきり遊べるようになったり、ぐっすりと眠れるようになったりと健康的な体を作る生活の土台が構築されます。
2. 食事を味わって食べられるようになる
食べ物のおいしさを感じられるようになるには、食事が楽しいと思えることが重要です。食育を通じて、様々な食材を食べたり、育てたり、触れたり、あるいは匂いをかいだりする経験を得ることで、子どもは食べ物に興味を抱き、おいしさを発見していきます。
3. 誰かと食事をとりたいと思う気持ちが育まれる
食育では、一緒に食べ物を育てたり、食事の後片付けをしたりと他者との関わりのなかで食への興味関心や理解を深めていきます。
子どもの頃から、食を通じたコミュニケーションを多く取ることで、一緒に食事をすると楽しいという経験が生まれ、その結果人の気持ちがわかるようにもなっていきます。
4. 食事作りや準備に関わりたいと思う
食べるだけが食育ではありません。誰かと一緒に調理をする経験を得られるのも食育のメリットです。子どもは調理を通じて自分が食べるものへの興味関心を深めていきます。その中で友達や家族とコミュニケーションを取り、生活していく力を身に着けていく過程で、食事作りや準備への興味も深まっていきます。
5. 食や健康に主体的に関わろうと思う
食育では、自分の体の仕組みについても学んでいきます。そのため、自分の健康と食の結びつきに気付きやすくなり、自ら食や健康について考える主体性が育まれます。
参考サイト:『楽しく食べる子どもに~食からはじまる健やかガイド|厚生労働省」
では、これら5つの力はどのような食育から生まれるのでしょうか。次の章では具体的なアイディアを5つ紹介します。
家庭でできる3つの食育のアイデア

ここでは、家庭でできる食育アイデアを3つを紹介します。
- 食材を一緒に調理する
- 家庭菜園やベランダ栽培をする
- 食や健康に関する絵本を一緒に読んでみる
食育において調理は非常に重要です。なぜなら普段自分が食べているものがどのように口に運ばれるのか、その過程を経験できるためです。また、食材に触れてみる、匂いをかいでみる、家族と話ながら調理してみるといった経験が食への興味につながります。
また、食材を一緒に育ててみることで、子どもは食材のありがたみに気付くこともできます。さらに、育てている食材に関する絵本や、健康に関する絵本を読むことで、より食への関心を深めることも可能です。
以下の記事では、保育園で行われている「食を通じた子どもの心の育みと活動」についてまとめていますので、ぜひ参考にしてみてください。
【関連記事】:現役栄養士に聞く! 食が育む、子どもたちの心|東京児童協会
ラグビー元日本代表、齋藤祐也さんの食育アイデア
当法人が実施した元ラグビー日本代表・齋藤祐也さんへのインタビューの中で、食育につながる幼少期のお話がありましたので、ご紹介します。
「幼いころの親の食育だったのか、嫌いなものはなくなんでも食べていました。私の母は料理が好きで、嫌いなものがあったらそれを工夫して出してくれていたのだと思います。なので、子どもの好き嫌いは保護者の一つの工夫で克服できるかもしれないですね。」
「また、将来体を大きくして、スポーツ選手になりたいという子の場合は、頑張ってご飯を食べるということもあるかもしれないですね。それに加えて友達と一緒にご飯を食べるというのは、友達との関係性向上にもつながるかもしれないですね。」
プロの世界で活躍した齋藤さんの経験もぜひ食育に生かしてみてください。
【乳児期~学童期】子どもの成長に合わせた食育を紹介

ここまで、食育の意義と具体的な方法を紹介しましたが、食育は子どもの年齢に合わせて適切に行うのがポイントです。そこで、乳児期、幼児期、学童期それぞれの時期に適した食育について解説します。
乳児期(0~1歳)
乳児期は生涯を通じての食欲や食べることに関する意欲の基礎を作ることが重要です。そのため、ミルクを飲むとき、離乳食を食べるときは目と目を合わせたり、声をかけたりして、食に対する安心感を得られるようにするのが重要です。
幼児期(2~5歳)
この時期は、食材に触れる、簡単な調理を体験するなどで、食への興味を育てるのがおすすめです。そのため、野菜や果物の栽培・収穫、季節の食材を一緒に調理して食べる、日本や海外の食文化を知るための学びとなる絵本やイベントへの参加などが理想です。
学童期(6~12歳)
学童期には、栄養バランスや食料の生産・流通から食卓までのプロセスなど、食に関する幅広い知識を習得したり、健康や福祉、環境問題や国際理解など様々な要素と、食の関係について学ぶことでさらに食を楽しむようになり、食の世界が広がっていきます。
参考:「食を通じた子どもの健全育成(-いわゆる「食育」の視点から-)のあり方に関する検討会」報告書について
食育を通じて子どもの豊かな食習慣を
食育は、子どもが健やかに成長し、健康的な食生活を送るための基盤を築く重要な取り組みであることを紹介しました。
食育には、規則正しい生活リズムの確立やコミュニケーション能力の向上など、多くのメリットがあります。特に幼児期から学童期にかけては、成長段階に応じた食育活動が効果的です。
家庭での食育では、親子で料理を楽しむ、食品選びを通じて食の大切さを学ぶなどの工夫がポイントです。この記事が、食育をはじめたり、いままで行っていた食育を見直したりするきっかけとなれば幸いです。